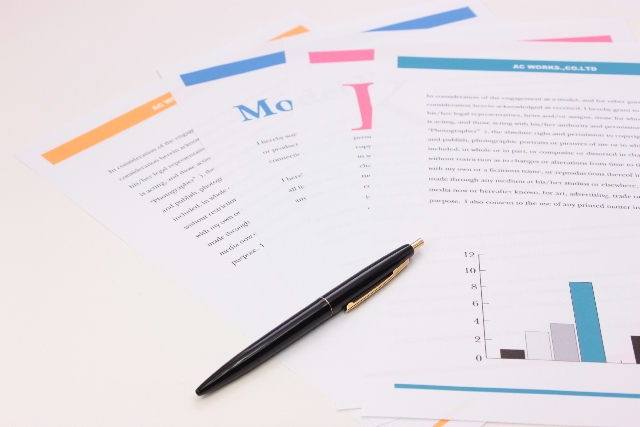


ハローワークインターネットサービスについて。
ハローワークに求職登録していない場合でも
ネットでハローワークの求人を見れますよね。
ですが
あそこに載っている場合は
必ずハローワークの紹介状が必要になるのでしょうか。
応募方法の欄には大抵はハローワークの紹介状が必要と書いてありますが
「TEL連絡後応募書類を送ってください」
と書いてありました。
ハローワークを通さず直接連絡していい場合もあるのでしょうか?
ハローワークに求職登録していない場合でも
ネットでハローワークの求人を見れますよね。
ですが
あそこに載っている場合は
必ずハローワークの紹介状が必要になるのでしょうか。
応募方法の欄には大抵はハローワークの紹介状が必要と書いてありますが
「TEL連絡後応募書類を送ってください」
と書いてありました。
ハローワークを通さず直接連絡していい場合もあるのでしょうか?
基本的にハローワークの求人に応募するには紹介状が必要だと考えておいたほうが良いでしょう。
ただし、在職中であると言った理由でハローワークで紹介を受けることが困難な場合は、直接求人先の企業に確認連絡をしてみることも問題ではありません。
注意しなければならないのは、求人票にトライアル求人併用といった給付金が関連する記載がある場合であり、自ら連絡されても必ずハローワークを通じて紹介状の発行を求められますので、この記載がある場合はハローワークで紹介を受けられたほうが無難です。
求人を出している多くの企業の場合、求人を確認して人材派遣会社の営業担当者が営業の連絡をしてくることもありますので、個人からの確認連絡を受け付けない場合が多くりますので、連絡される際は注意が必要ですね…
ただし、在職中であると言った理由でハローワークで紹介を受けることが困難な場合は、直接求人先の企業に確認連絡をしてみることも問題ではありません。
注意しなければならないのは、求人票にトライアル求人併用といった給付金が関連する記載がある場合であり、自ら連絡されても必ずハローワークを通じて紹介状の発行を求められますので、この記載がある場合はハローワークで紹介を受けられたほうが無難です。
求人を出している多くの企業の場合、求人を確認して人材派遣会社の営業担当者が営業の連絡をしてくることもありますので、個人からの確認連絡を受け付けない場合が多くりますので、連絡される際は注意が必要ですね…
以前勤めていた会社に、離職票の送付を依頼したのですが、離職票を送ってくれません。
問い合わせの電話をしても、無視されてしまいます。
職安に相談した所、職安は介入できないと言われました。
そこの会社は悪質で、事務管理もずさんでした。離職票を請求しても、送ってもらえないだろうと思っていました。
受けられるはずの失業給付が、離職票がないばかりに受けられず、困っています。
同じような経験をされた方、このような問題に詳しい方のアドバイスを、お願い致します。
本当に困っています。
問い合わせの電話をしても、無視されてしまいます。
職安に相談した所、職安は介入できないと言われました。
そこの会社は悪質で、事務管理もずさんでした。離職票を請求しても、送ってもらえないだろうと思っていました。
受けられるはずの失業給付が、離職票がないばかりに受けられず、困っています。
同じような経験をされた方、このような問題に詳しい方のアドバイスを、お願い致します。
本当に困っています。
悪質ということで雇用保険未加入とかはないですか?
雇用保険を引かれているにも未加入事案もあります。もちろん悪質なケースです。でも、安心してください。そういった悪質な場合は何十年でも遡って加入出来ます。給与から引かれていなくて未加入だった場合は知らなかっただけで悪質とは言えず、もちろん本人も雇用保険未加入の事実もわかる訳ですので、遡って加入出来るのは2年間です。
ハローワークでは関与出来ないと言われたとありますが、指導して貰えるハズですよ。通常2週間くらい時間が掛かるものですが、遅くとも1カ月は掛からないと思います。その頃までに頂けないのであれば指導してもらって下さい。
でも本当に悪質な会社の場合、指導も無視もあり得ますので、根気勝負になるかも知れません。
雇用保険を引かれているにも未加入事案もあります。もちろん悪質なケースです。でも、安心してください。そういった悪質な場合は何十年でも遡って加入出来ます。給与から引かれていなくて未加入だった場合は知らなかっただけで悪質とは言えず、もちろん本人も雇用保険未加入の事実もわかる訳ですので、遡って加入出来るのは2年間です。
ハローワークでは関与出来ないと言われたとありますが、指導して貰えるハズですよ。通常2週間くらい時間が掛かるものですが、遅くとも1カ月は掛からないと思います。その頃までに頂けないのであれば指導してもらって下さい。
でも本当に悪質な会社の場合、指導も無視もあり得ますので、根気勝負になるかも知れません。
現在務めている会社で、お盆と正月が計画的有休にされようとしています。
労使協定を結んでいないので、結ばなければ実行はされないと考えているのですが、そのような労使協定を結ばない方が得
策なのか、計画的有休にしたほうが良いのかご意見頂ければと思います。
背景は以下に記載させて頂きます。
昨年は、会社から支給する休暇です。と言われ、お盆と正月を休みました。
入社したときも、お盆と正月は会社から支給する休みと言われました。
ですが、書面などでの記録はありません。
就業規則は見たことがありません。今、作成中のようです。存在するのかもしれませんが、周知されたことはありません。(常駐社員10名以上の企業です)
①以前に遡って、昨年度以前のお盆と正月も計画的有休にしようとしています。計画的有休にしないと、ただの休みなる為、減給になるので有休にしたほうが良いと言われています。就業規則が出来上がり、労使協定を結んだとして、過去の休暇についてまで遡ることはできるのでしょうか?
②経営事情などもあるので、今年から変更と言うのは仕方ない?のかもしれませんが(労使協定で合意すれば)、過去の休暇まで対象になるのは、法律的にいかがなものでしょうか?
③また、もしハローワーク等でお盆と年末年始休暇がある旨の記載があった場合は対抗出来るのでしょうか?
④そもそも就業規則がない時点で間違っていると思いますが、就業規則が出来上がって拘束される前であれば、もし様々な面で訴えたとしたら有利になるのでしょうか?従業員の不満が溜まっているので、もしもの話ですが…
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
労使協定を結んでいないので、結ばなければ実行はされないと考えているのですが、そのような労使協定を結ばない方が得
策なのか、計画的有休にしたほうが良いのかご意見頂ければと思います。
背景は以下に記載させて頂きます。
昨年は、会社から支給する休暇です。と言われ、お盆と正月を休みました。
入社したときも、お盆と正月は会社から支給する休みと言われました。
ですが、書面などでの記録はありません。
就業規則は見たことがありません。今、作成中のようです。存在するのかもしれませんが、周知されたことはありません。(常駐社員10名以上の企業です)
①以前に遡って、昨年度以前のお盆と正月も計画的有休にしようとしています。計画的有休にしないと、ただの休みなる為、減給になるので有休にしたほうが良いと言われています。就業規則が出来上がり、労使協定を結んだとして、過去の休暇についてまで遡ることはできるのでしょうか?
②経営事情などもあるので、今年から変更と言うのは仕方ない?のかもしれませんが(労使協定で合意すれば)、過去の休暇まで対象になるのは、法律的にいかがなものでしょうか?
③また、もしハローワーク等でお盆と年末年始休暇がある旨の記載があった場合は対抗出来るのでしょうか?
④そもそも就業規則がない時点で間違っていると思いますが、就業規則が出来上がって拘束される前であれば、もし様々な面で訴えたとしたら有利になるのでしょうか?従業員の不満が溜まっているので、もしもの話ですが…
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
①労使協定を締結、就業規則に定めても、労働者の不利になることは、遡って適用することができません。通常、計画的付与されることは、労働者の時季指定権が消滅する不利なことですから遡って適用することはできないでしょうね。まぁ、遡って適用されることで賃金が支払われることで時季指定権の消滅を上回るくらい有利になるのなら、遡って適用できるかもしれませんが、最終的には裁判をしてみないと分かりません。
②「①」で回答したように、労働者の不利になることは遡って適用することはできません。
③ハローワークの求人票は、法的には申込みの誘引といって広告のようなものですから、実際の労働条件と違っていても、直ちに問題になりません。このことを理由に争うことは難しいでしょうね。
④労働者が、10人以上いるのに就業規則ない、周知されていないのなら、違法になります。今後、就業規則を作成するとしても、労働者・過半数代表者の同意が要りませんので、法律に反しない限り、会社が自由に決めることができます。ただし、労働条件の不利益変更になる場合は合理的なものでなければなりませんし、労働者に不利になることは遡って適用することはできません。なお、変更が合理的であるかどうかは、最終的に裁判をしてみないと分かりません。
<追加>
有給休暇の計画的付与は、労使協定の締結が条件ですから、就業規則の作成・変更と違い、過半数代表者の同意が必要です。
②「①」で回答したように、労働者の不利になることは遡って適用することはできません。
③ハローワークの求人票は、法的には申込みの誘引といって広告のようなものですから、実際の労働条件と違っていても、直ちに問題になりません。このことを理由に争うことは難しいでしょうね。
④労働者が、10人以上いるのに就業規則ない、周知されていないのなら、違法になります。今後、就業規則を作成するとしても、労働者・過半数代表者の同意が要りませんので、法律に反しない限り、会社が自由に決めることができます。ただし、労働条件の不利益変更になる場合は合理的なものでなければなりませんし、労働者に不利になることは遡って適用することはできません。なお、変更が合理的であるかどうかは、最終的に裁判をしてみないと分かりません。
<追加>
有給休暇の計画的付与は、労使協定の締結が条件ですから、就業規則の作成・変更と違い、過半数代表者の同意が必要です。
関連する情報